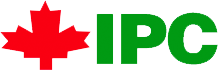ブレーキユニットのサプライヤーは、周波数変換器とモーターはどちらも高出力の電気機器であることをご承知おきください。電流が回路を流れると、抵抗が存在するため、ジュールの法則に従って熱作用が生じ、発熱します。高出力電流は比較的大きな電流値を持つことが多く、発熱現象が発生します。一般的に、手に熱く感じることはないと判断されますが、非常に熱く感じる場合は、速やかに対処する必要があります。
選択の正確さに注意する
モーターは機器の動作の心臓部であり、ほぼすべての負荷の動力源です。機器設計においては、負荷に必要なトルクと出力を総合的に考慮し、適切なモーター出力とトルクを選択する必要があります。モーターの容量が小さすぎると、小さな馬が重い車両を引っ張っているようなものです。当然、モーター自体は過負荷状態で動作し、激しい熱を発生します。
同様に、周波数変換器の仕様も小さく選択した場合、定格電流を超える電流を長時間流すと周波数変換器は激しい熱を発生し、すぐに問題が発生して焼損します。
選択肢が少なすぎるため、対応策としては大型モデルへの買い替えしかありません。これは厳格な要件であり、近道はありません。タイムリーに対処しなければなりません。たとえ既存のものを解体して中古品として売却するとしても、使い続けた方が良いでしょう。生産が遅れたり、発熱などによる爆発や火災が発生するような問題があれば、それは一大事です。
一部の負荷は重くないように見えるかもしれませんが、頻繁な始動と停止を伴い、使用するには電力増幅も必要になります。そうしないと、依然として上記のような問題に直面することになります。
機器と負荷の問題
機械設備や負荷に異常がある場合、例えば伝動機構のギアやベアリングが損傷すると、抵抗が増加し、モーターの出力も増加します。深刻な場合には、モーターが失速し、電流が非常に高くなることもあります。ほとんどの周波数変換器は過負荷と過電流を引き起こし、アラームシャットダウンにつながりますが、中には危険な状態にあるものや、周波数変換器の保護パラメータが適切に設定されていない場合、発熱などの異常現象を引き起こすこともあります。このような状況では、当然のことながら、機械設備と負荷から問題を解決する必要があります。
例えば、周波数変換器は一部の液体搬送ポンプや給気ファンを制御します。配管の汚れや曲がりにより、高い抵抗が発生し、モーターや周波数変換器に過大な電流が流れる可能性があります。これらの配管は、適時に清掃・処理する必要があります。
周波数変換器とモーター自体の問題
モーターを長期間使用すると、絶縁性能の低下やベアリングの固着などにより、高電流が発生し発熱する恐れがあります。また、モーターと負荷の接続部が摩耗したり、三相不平衡やモーター固定装置の緩みなどにより、異音や発熱が発生することもあります。
周波数変換器内の特定のコンポーネントの老朽化、ベクトルパラメータとモータマッチングの偏差、トルクブーストなどのパラメータの過剰な設定、加速および減速時間の短縮、周波数変換器の搬送周波数の低下などにより、モータと周波数変換器が同時に加熱される可能性があります。
モーターと周波数変換器間の接続線は、一般的に長すぎると減衰や波形歪みが発生するため、長すぎないようにする必要があります。長すぎる場合は、専用の周波数変換器と追加のリアクトルを使用して対処する必要があります。
急速なブレーキが必要な状況では、ブレーキ力に応じて適切なブレーキ抵抗器とブレーキユニットを選択する必要があります。
低周波状態での長期作業
一般的に、モータを8Hz未満で動作するように設計することは推奨されません。ベクトル制御の周波数変換器を使用する場合でも、このような使用は可能な限り避けるべきです。これは主に、低周波数域で波形が著しく歪み、正弦波から大きく離れるため、モータ性能の低下、トルクの著しい減衰、発熱につながるためです。この目標は、伝達比を高め、周波数変換器の出力周波数を上げることで達成できます。
低周波状態で長時間動作させる必要がある場合は、専用の可変周波数モーターを使用したり、強制空冷や水冷などでモーターを冷却したりすることもできます。
使用環境を最適化する
かつては経済状況が悪かったため、多くの中小企業は独立した制御室を設計していませんでした。また、制御室があっても空調設備を設置していませんでした。しかし、状況が改善した現在では、空調設備を備えた制御装置に周波数変換器などのコンポーネントを設置することが十分に可能になっています。これにより、周波数変換器の温度が最適な状態に保たれ、発熱が少なくなり、粉塵などの発生を抑えることで寿命が延びます。全体として、これは比較的良い投資と言えるでしょう。